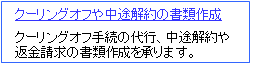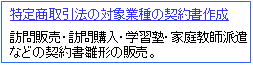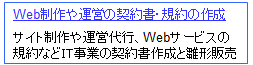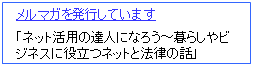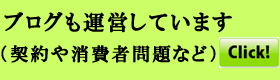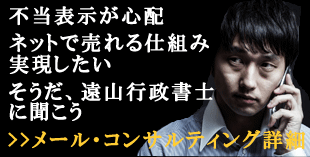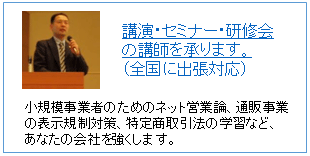SuicaやGooglePlayギフトカード等の電子マネー、ビットコインやイーサリアム等の暗号資産といったデジタルでの金銭的価値のある情報流通手段が増えています。
こうしたデジタル資産はスマートフォンだけで取引が可能で、セキュリティ管理に注意をすれば安全に保管もできるので、現金に代わる財産として積極活用している方も多いでしょう。
ただ、これらのデジタル資産を相続する場合には、現金や銀行預金のように単純にはいかないので気を付けなくてはなりません。
銀行預金を相続する場合は、故人が用意した遺言書か、相続人全員で作成した遺産分割協議書を銀行に提出し、口座解約をして現金を分配するという手順になります。
その際に銀行通帳と銀行届出印鑑、戸籍謄本や相続人の本人証明等の提出も求められます。
それもなかなかに面倒な手続ですが、デジタル資産の相続に比べれば簡単な手続といえます。
デジタル資産については、まずその存在を特定させることから始めなくてはなりません。
銀行預金であれば、通帳さえ見つかれば後は何とかなります。
しかし、デジタル資産に関する情報はスマートフォンかパソコンから情報検索をしないと、その存在にさえたどり着けません。
端末の起動時にパスワードロックされていたら、入り口にも立てないです。
端末にログインできたとしても、電子マネーや暗号資産の所在情報やパスワードが次の壁になります。(指紋認証だと相続人はアクセスもできません)。
そうした事情でデジタル資産があることの把握が遅れると、長期間放置でサービス解約となってしまうケースもあるでしょう。
つまりデジタル資産については、デジタル資産の保有者がアクセス情報やパスワード等を書き残していないと、遺族はそれを相続するのが困難になります。
そのような事態を避けるには、相続のために事前に現金化しておくか、デジタル資産の情報を遺言書の財産目録に記載しておく必要があります。
自筆の遺言書なら一人で作成できますが、書き残しておくべき情報に不足があるとデジタル資産については相続ができないというリスクがあります。
相続の手続をスムーズに進めるためには、遺言書の内容について専門家のチェックを受けた方が安心できます。
デジタル資産の取り扱いを含めて、遺言書の起案作成をしたい場合は、当行政書士事務所の以下のリンク先ページをご参照ください。
デジタル資産の相続のための遺言書と死後事務委任契約書の作成|遠山行政書士事務所